現代の行動理論は認知を含んでいる。普通の人にとっては心と体、認知と行動という区別“心身二元論”を元にして考えることが多いだろう。心がこうだから、考えがああだから、結果としてこう行動するというように考えるだろう。行動理論はこのありきたりの考え方への挑戦である。
常識心理学の二つの前提
この常識的発想には二つの特徴がある。1つが因果論である。何かが起きるのは原因があるからだと考える。精神医学では精神疾患を原因によって外因性と内因性、心因性に三分類する。CBTの認知モデルでも不合理な認知やスキーマのような心の状態が原因であり、その結果として病的行動が現れるとする。治療の最初のステップは心の中にある原因を同定することである。原因→結果という矢印の向きは一定である。2つめがパターンに対するこだわりである。“手を洗えば不安が減る”のようなパターンに気付くとそれに“動因低減”などの名前を付けて、他にも当てはめようとする。パターンが生じる場合と生じない場合の頻度をカウントしてデータにまとめるようなことはしない。パターンを見つけるのは得意だが、量や頻度の変化を経時的に把握することは苦手である。
心→体という因果論で物事をとらえ、心の出来事をパターンに当てはめ、それが当てはまらない場合は無視する、このような考え方は普通の人が日々していることである。これを常識心理学と呼ぶ(Rips & Conrad, 1989)。
現代の行動理論、心の哲学、比較認知科学
常識では行動理論は行動だけを扱うと思うだろう。100年前の行動主義者はそのとおりだと答えていた。現代の行動理論はそうではない。考えること自体、推論自体を行動理論の対象として考えるようになった。この領域を特に心の哲学と呼ぶ。100年前の行動理論の発展には動物実験の知見が寄与した。近年の心の哲学の発展についても同じである。100年前との違いはコンピューターなどを使い、工夫を重ね、言語を持たない動物の“心”を-あらためてこれを認知と呼ぶことにしよう―3、40年前の心理学者には想像もつかないほど詳しく解明できるようになったことである。この領域を特に比較認知科学と呼ぶ(松沢1992)。この領域の科学者は、言語があるからヒトがチンパンジーよりも複雑な思考ができるとか、大脳新皮質があるから哺乳類は鳥類よりも賢いなどとは考えない。それぞれの種、それぞれの個体がそれぞれの環境の中で賢い行動をしており、その行動には環境からの学習によって生じる部分が大きいと考える。大脳新皮質だけ与え、適切な学習環境は与えないとしたら人も動物も認知を発達させることはできない。
しかし、こうなる前は行動理論はなかば終わった理論のように思われていた。数十年ほど前にさかのぼってみよう。
20世紀後半の行動理論と“認知革命”
スタートの時点ではワトソンやスキナーなど行動主義者の主張は行動の説明から常識心理学を排除することだった。排除しても行動を記述し、予測し、コントロールできることを実証し、アカデミックな心理学は行動主義一色になった。そして論文からも“心”を排除するようになった。この世代-第一世代と呼ぼう-の行動療法家の中には普段の会話の中であっても“認知”という言葉に対して嫌悪感を示す人がいるぐらいである。しかし、記憶や価値判断、因果推論を昔の水準のパブロフ条件づけや道具的条件づけで予測・制御できたわけではない。行動理論が臨床に応用された初期の一例が恐怖症に対するエクスポージャー療法である。そこから広げようとすると動機づけや言語に縛られるルール支配行動も扱わざるをえない。一方、行動理論側は“認知回避”を続け、動機づけなどに対する答えを持たず、それが1950年代に始まった心理学上の“認知革命”を呼び込む結果になった。“心の哲学”や“比較認知科学”はまだ生まれていない。実験心理学上の認知革命は臨床にも広がり、行動療法家はマイケンバウムの認知行動療法、ベックの認知療法に入っていかざるを得なかった。
今、起きつつある変化
「行動主義は終わった」と主張する精神科医がいる(加藤2007)。たしかに認知を排除する行動主義は終わった。2014年に行動療法学会は認知行動療法学会にその名称を変えた。この名称変更は一般には行動療法が認知療法に負けた結果として受け取られている。用語出現頻度の点ではそのとおりだ。医中誌で2017年以降を検索すると“認知療法”+“認知行動療法”が2113件、“行動療法”が681件になる。この差は今後ますます広がっていくだろう。
しかし、認知を排除する行動主義の終わりは、“認知主義”の始まりではない。行動主義を信奉する実験心理学の領域でも名称変更が起こっている。2014年、“Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes“誌は下の名前を“Animal Learning and Cognition”に変えた。動物の学習で認知を扱うことを看板にしたのである。
常識心理学に従えば“言語があるから考えられる”と考える。デカルトの「我思う、ゆえに我あり」が常識である。現代行動理論はその先を行く。行動経済学のカーネマンとトベルスキーはプロスペクト理論を立ち上げた。考えるという点でも思考バイアスの点でも人と実験用マウスは変わらないと考える。環境条件を記憶し行動を変えるということであれば一個の細胞でもできると行動理論なら考える。言葉や脳のあるなしと“認知”は無関係である。
行動主義の目的に戻る
行動理論のスタートは正常な動物の生理現象の研究である。パブロフは犬の唾液腺の働きから条件反射を見出した。ソーンダイクはネコの非反射的行動が経験を通してどう変化するのかを研究するうちに効果の法則を見出した。どちらも今は創始者には想像もつかないほどはるかに拡張された概念になっている。名前はレスポンデントとオペラントに変わった。記憶再生や価値観、言語や思考も扱えるようになった。ここまで拡張されてもパブロフ、ソーンダイクの時代と変わらないものがある。病理ではなく生理に、原因探しではなく予測と制御に焦点を当てることである。
行動理論は体と心を分けないのと同じように正常と異常も分けない。ある社会が異常だと呼ぶ行動があるなら、異常とされるのはどういう場合なのか、機能的に等価な他の行動は何なのか、それに代替すると社会がどう受け取るのか、と具体的な行動に分けて考える。原因と結果すら分けない。普通なら、異常な行動が原因で、結果として社会が受け入れないと考える。行動理論なら、社会が受け入れないが原因で、結果として異常な行動が現れるというのも選択肢の一つにする。
犬の場合なら、なぜ犬は言葉をしゃべれないのか?という問いではなくどうすれば犬と人との間のコミュニケーションが成立するのか?という問いをたてる。犬と人がどう違うかよりも2つの種の間で機能的に等価な行動は何かを考える。実は犬はアイコンタクト行動の点で人にとても近い。
それでも常識には勝てない
行動理論は犬のトレーニングにも実績を出している。犬の分離不安や強迫症に認知療法をしようという人はいないだろう。一方、犬の行動はもちろん、表情認知も扱える行動理論が人の認知を扱い、変えることができるのは当然ではないだろうか?もし精神療法の対象に人だけでなく、犬や猫も加えることにしたら、行動療法が認知療法に勝つのははっきりしている。
残念なことが一つある。犬や猫は治療の感想を書き残してくれず、飼い主は相変わらず常識心理学にとらわれていることである。どれだけトレーナーが行動理論に詳しく、実際の応用にも優れた人であったとしても、飼い主の感想は「トレーナーの真心が私のソラ君を治してくれました」になってしまうだろう。
【さらに詳しく知るための文献】
[1] 原井宏明. (2010). 対人援助職のための認知・行動療法―マニュアルから抜けだしたい臨床家の道具箱. 東京: 金剛出版.
Pearce, J. M., 石田雅人, 石井澄ら (1990). 動物の認知学習心理学. 北大路書房
Kahneman, D., & 村井章子. (2012). ファスト&スロー : あなたの意思はどのように決まるか? 上下. 東京: 早川書房.
【参考・引用文献】
松沢哲郎. (1992). 意識の進化:動物の意識. 生体の科学, 43(1), 7–11.
Miller, R. R. (2014). Editorial explaining the change in name of this journal to Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Cognition. Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Cognition, 40(1), 1–1
Rips, L. J., & Conrad, F. G. (1989). Folk Psychology of Mental Activities. Psychological Review (Vol. 96).
加藤隆弘. (2017). 脳科学と精神分析の架橋. 臨床心理学, 17(3), 350–351.

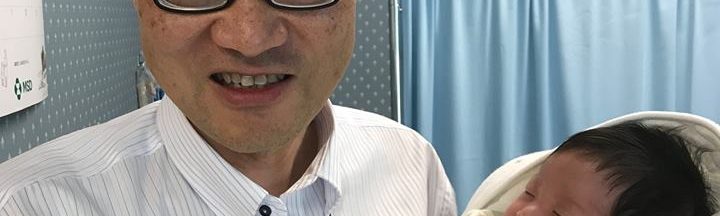



認知革命の時期とJournal of Experimental Psychology: Animal Learning and Cognitionについての記載を書き換えました。ご指摘いただいた方に感謝いたします。
規定に合わせて1/2に短縮化したものをアップします。
—-
現代の行動理論は認知を含む。普通なら心と体、認知と行動という区別“心身二元論”を元にして考えるだろう。心がああだから、こういう考えを持つから、結果としてそう行動するというように考える。行動理論はこの常識への挑戦である。
常識心理学
常識的発想には因果論とパターン重視の二つの特徴がある。何かが起こるのは原因ゆえだと考えるのが因果論である。認知モデルでは不合理な認知のような心の状態が原因であり、その結果として病的行動が現れるとする。治療の最初のステップは心の中にある原因を同定することであり、次は原因を変えることである。結果を先に変えるという発想はない。パニック症の患者において身体感覚に対する解釈に独特のパターンがあることに気付くと“破局的解釈”という名前を付けて他にも当てはめようとする。パターンが生じる場合と生じない場合の頻度をカウントしてデータにまとめるようなことはしない。パターンを見つけるのは得意だが、量や頻度の変化を経時的に把握することは苦手である。
因果論で物事をとらえ、心の出来事をパターンに当てはめることは子供から老人までどんな人でも日々の習慣にしていることである。日常生活はそれでなんとかなっている。これを常識心理学と呼ぶ(Rips & Conrad, 1989)。
心の哲学、比較認知科学
常識では行動理論は行動だけを扱う。100年前の行動主義者もそのとおりだと答えていた。現代の行動理論はそうではない。考えること自体も対象にするようになった。この領域を特に心の哲学と呼ぶ。研究の基礎は昔と同じく動物実験にある。昔との違いはコンピューターなどを使って工夫し、動物がゲームのように楽しんで知的な実験に参加するようになったことである。この結果、言語を持たない動物の“心”を-これを認知と呼ぶことにしよう―詳しく解明できるようになった。動物の認知研究を比較認知科学と呼ぶ(松沢1992)。行動理論では、言語があるからヒトがチンパンジーよりも複雑な思考ができるとか、大脳新皮質があるから哺乳類は鳥類よりも賢いとは考えない。それぞれの種、それぞれの個体がそれぞれの環境の中で賢い行動をしており、その行動には環境からの学習によって生じる部分がある。大脳新皮質だけ与え、適切な学習環境は与えないとしたら人も動物も認知を発達させることはできない。
しかし、少し前まで行動理論は賞味期限切れだと思われていた。数十年前にさかのぼってみよう。
20世紀なかばの認知革命
スタート時点の行動主義者の主張は常識心理学を排除することだった。排除しても行動を予測し、制御できることを実証し、アカデミックな心理学は行動主義一色になった。論文からも“心”や“認知”を排除するようになった。
しかし、記憶や価値判断、因果推論を昔の水準のパブロフ条件づけや道具的条件づけで予測・制御できたわけではない。行動理論が臨床に応用された初期の一例が恐怖症に対するエクスポージャー療法である。応用を広げようとすると動機づけや言語に縛られるルール支配行動も扱わざるをえない。一方、行動理論側は“認知回避”を続け、動機づけなどに対する答えを持たなかった。それが20世紀後半の“認知革命”を呼び込む結果になり、そして実験心理学上の認知革命は臨床にも広がり、行動療法は認知行動療法に名前を変えた。
今、起きつつある変化
「行動主義は終わった」という主張がある(加藤2007)。たしかに認知を排除する行動主義は終わった。しかし、認知を排除する行動主義の終わりは、“認知主義”の始まりではない。実験心理学は認知を正面から扱うようになった。2014年、“Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes“誌は下の名前を“Animal Learning and Cognition”に変えた。
常識心理学に従えば“言語があるから考えられる”と考える。デカルトの「我思う、ゆえに我あり」が常識である。現代行動理論はその先を行く。行動経済学のカーネマンとトベルスキーはプロスペクト理論を立ち上げた。思考バイアスの点で人と実験用マウスは変わらないと考える。環境条件を記憶し行動を変えるということであれば一個の細胞でもできると考える。言葉や脳のあるなしと“認知”は実は無関係なのだ。
行動主義のスタートに戻る
行動理論のスタートは正常な動物の生理現象の研究である。パブロフは犬の唾液腺の働きから条件反射を見出した。ソーンダイクはネコの非反射的行動が経験を通してどう変化するのかを研究するうちに効果の法則を見出した。どちらも今は創始者には想像もつかないほどはるかに拡張された概念になっている。ここまで拡張されても100年前と変わらないものがある。病理ではなく生理に、原因探しではなく予測と制御に焦点を当てることである。
行動理論は正常と異常を分けない。犬と人も分けない。なぜ犬は言葉をしゃべれないのか?という問いではなく、どうすれば犬と人との間のコミュニケーションが成立するのか?という問いをたてる。犬と人の間で機能的に等価な行動は何かを考える。実は犬はアイコンタクト行動の点で人にとても近い。
行動理論は犬のトレーニングにも実績を出している。犬の分離不安や強迫症に認知療法をしようという人はいないだろう。犬の行動はもちろん、表情認知も扱える行動理論が人の認知を扱うのは当然ではある。
【さらに詳しく知るための文献】
[1] 原井宏明. (2010). 対人援助職のための認知・行動療法―マニュアルから抜けだしたい臨床家の道具箱. 東京: 金剛出版.
Pearce, J. M., 石田雅人, 石井澄ら (1990). 動物の認知学習心理学. 北大路書房
Kahneman, D., & 村井章子. (2012). ファスト&スロー : あなたの意思はどのように決まるか? 上下. 東京: 早川書房.
【参考・引用文献】
松沢哲郎. (1992). 意識の進化:動物の意識. 生体の科学, 43(1), 7–11.
Miller, R. R. (2014). Editorial explaining the change in name of this journal to Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Cognition. Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Cognition, 40(1), 1–1
Rips, L. J., & Conrad, F. G. (1989). Folk Psychology of Mental Activities. Psychological Review (Vol. 96).
加藤隆弘. (2017). 脳科学と精神分析の架橋. 臨床心理学, 17(3), 350–351.