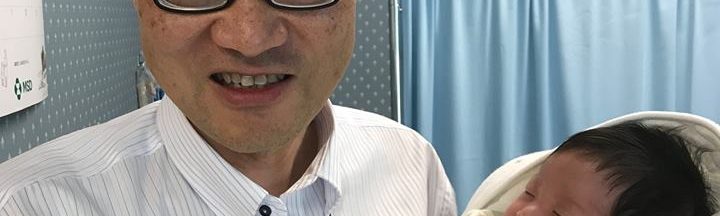注意 この原稿は草稿です。最終版ではありません。引用などはお控え下さい。
I. どの技と工夫、知を使うのか?
1. 15のコツ
この本には15の精神療法のコツが並んでいる。それぞれの著者はその領域の専門家である。それぞれが読者である精神科医に対して“ここだけはぜひ伝えたい勘所だ”と訴えている。15個の勘所をバラバラに伝えられた読者のあなたはどうするのだろう?一つ一つ15の勘所を患者に試してみようとするのだろうか?全部に目を通せば、それで15の精神療法を一通り身につけたことになると思うのだろうか?
おそらくどの著者であっても15の勘所を一度に一人の患者に当てはめるのはやめてくれと言うだろう。ある精神療法には特定の適応があり、ある勘所にはそれを使うべきタイミングや状況があると言うだろう。
常識では“適応→特定の精神療法→状況→コツ”のような直線的な関係を考える。ある精神療法にはそれが適している診断・状態名があり、あるコツにはそれを使うべき状況があり、こうした組み合わせを知ることもコツの一つだというだろう。組み合わせがわかるためには知識を得るだけでは足りない、体験的ワークショップを受講し、スーパービジョンを受けながら実際の症例を担当するという経験が必要だと言うだろう。学会員になり、資格認定を受けろと言うかもしれない。無資格者がその精神療法をしていると公言することは禁止と言うかもしれない。
知識だけでは足りないのは私もその通りだと思う。座学だけで精神療法の勘所が分かった、今日からコツを使おうと思うような精神科医は臨床に向いていない。ただし、資格認定には私には異見がある。行動療法の実践に関しては資格無用である。クリニックの受付事務員にもできる行動療法の技法がある。最初の受付の電話対応で、動機づけ面接ができるかどうかは治療成績に影響する。調剤薬局の薬剤師が患者に一言声をかけるかどうかで、患者の薬物アドヒアランスが変わる。つまり、患者側の適応と状況に加えて、第3の要因、介入者にも合わせて使えるコツがある。
一方、適応・状況・介入者と分けて述べるだけでも大変なことになる。適応と状況、介入者を図にすれば平面図では済まない。これだけで立方体になってしまう。
2. 技法の山
行動療法には様々な顔があるが、その一つにうんざりするぐらいある技法の数々を上げることができる。私が行動療法を学び始めた、30年前に出版された行動療法事典(Bellack, Hersen, & 山上, 1987)には100以上のエントリーがある。それから、さらに新しい技法が生まれてきている。既存の技法を組み合わせた治療パッケージや疾患別・問題別にデザインされた治療プログラムもある。もともと動物実験の知見から始まったものだから、言語が通じない相手に対する行動療法もある。言語のない自閉症者はもちろん、記憶が5分と持たない認知症者、犬や猫、鳥に対しても行動療法ならできる。行動全てに適応できるのだから、就労支援や生活習慣病、アレルギー疾患、便秘などにも使える。
私の体験の中から、行動療法の幅の広さを示す例を2つとりあげてみよう。患者が自分で症状をチェックし、記録するセルフモニタリングは行動療法の勘所中の“勘所”と言えるぐらい、基本的な技法である。30年前から今まで私も使い続けている(原井, 1997)。もう一つの勘所は私にとっては2003年頃から使えるようになったMotivational Interviewing(動機づけ面接)(原井, 2012)である。
2008年、1型糖尿病を専門にする小児科医から突然、動機づけ面接を個人指導してほしいという依頼がきた。それまでの1型糖尿病に関する私の知識は、高校の部活の後輩がインシュリン自己注射をしていたことぐらいだった。デモンストレーションをしてみせよう思っても、HbA1cの正常値も知らない私では医者役になれない。指導の前に実際の診療場面を見せてもらうことにした。行ってみたら、そこではSMBG(Self-Monitoring of Blood Glucose)が当たり前になっていた。患者自身で血糖を毎日自己測定し、記録を取ることである。糖尿病専門の小児科診察室で私はセルフモニタリングを再発見したわけである。2015年、さらに縁があって、関節リウマチを専門にしている医療者に動機づけ面接を教えることになった。それまで私が持っていた膠原病に関する知識はステロイドホルモンの使用ぐらいである。抗リウマチ薬(DMARDs、Disease-Modifying Antirheumatic Drugs)や生物学的製剤など初耳だった。関節リウマチにおける動機づけ面接のエビデンス(Georgopoulou, Prothero, Lempp, Galloway, & Sturt, 2015)を私は全く知らなかった。
こうなると、30年間どっぷりと行動療法に浸かっている私にも、その全貌をつかむことはもはや不可能だ。100以上ある技法について、適応・状況・介入者をリストし始めたら、いったいどういうことになるか想像してほしい。さらに言えば、30年間に私自身がやっていたことが大きく変わった。たとえば、アクセプタンス&コミットメント・セラピー(Acceptance & Commitment Therapy、以下ACT)(Hays C. & Smith, 2010)を知る前、2000年より前に私がやっていたことは今のやり方とは別世界である。昔やっていたことは今でも行動療法と呼ばれているが、私が今やっている行動療法と並べると、とても同じものとは思えないぐらいの違和感がある。そして、この違和感を説明するためには方法論的行動主義と徹底的行動主義の違い、機能的文脈主義の説明が必要になる。世界観や強化随伴性にも手を出さなければならない。こんな哲学的衒学趣味に誰が興味を示すだろうか?20代の私も肥前療養所でフッサールの現象学(松尾, 1986)を勧められたがすぐに挫折した。
3. 2種類の理由
私には勘所を伝えるのは無理そうだ。しかし、なぜ私が30年間も行動療法を続けているのか、なぜその間に考え方や技法を変えてきたのか、その理由を伝えるぐらいはしたい。
理由は“始めた理由”と“続ける理由”に分けられる。普通なら、行動療法を“始めた理由”から始めたいところだが、残念ながら、私の場合、偶然が一番の理由である。行動療法に触れた理由は、神戸大から紹介された肥前療養所にたまたま山上敏子先生がおられて、「あんたは英語ができるから」と通訳の仕事を依頼された、それ以外にはない。「行動療法を勉強したくて肥前に行きました」とかと言ったらでっち上げにも程がある。行動療法と相性が良いからとか、エビデンスがあるからとか、学会が育ててくれたからとか、と言えば、すべて後付け理由付け、辻褄合わせのための「ストーリー」である。これは行動療法だけではない。たとえば精神科を選んだ理由は、卒後は生化学教室で基礎研究をするつもりだったのに、そこに気の合わない先輩がいるのにたまたま気付いたせいである。
しかし、何かを30年も続けたなら、そこには“続ける理由”がある。行動療法で言えば、続ける理由とは行動の結果であり、結果が行動療法を続けるという行動を強化したことになる。この30年間、私が試してきた様々な行動療法はその結果によって弱化されたり、強化されたりを続けて、変化を続けた。このように行動療法が私に及ぼした働き、つまり機能こそが私が行動療法を続ける理由である。
行動療法には機能重視という実用主義の伝統がある。頭の中だけで理屈をこねくり回して生み出された高尚な哲学ではなく、ラットの世話に苦労しながら生み出された動物実験の結果がベースにある。犬やヒトはもちろん、ゾウリムシのような単細胞生物(Fernando et al., n.d.)でも、光信号と危険の関係を学習したならば、パブロフ恐怖条件づけが成立しているという。起源も名前も異なる治療技法があるとしよう。その技法群がもたらす結果が全て同じならば、行動療法は、それらはみな“同じ機能を持つ”と言い、一つにまとめてしまう。たとえば、逆説志向はフランクルのロゴセラピーからきた概念であり、インプロージョンは精神分析から来ている。どちらも不安・回避が下がるという機能は同一だから、エクスポージャーにまとめてしまう。
30年間、100は行かないにしても、私も数え切れないぐらいの技法を試してきた。診断もさまざまだし、行った状況も病院やクリニック、患者の自宅など様々である。それぞれ多種多様だが、目指してきた結果は片手の指で数えられるぐらいしかない。言い換えれば私の行動療法の機能は2,3しかない。ではその機能とはなんだろうか?患者に感謝されるから?病気を治せるから?社会に評価されるから?
II. 強化と弱化
1. 思わぬ結果が行動を支配する
人がある行動をする。何か起こる。変わる。消える。窓を開ければ温度が変わる。変わるものは外側のこともあるし、内側のこともある。空気を吸えば気分が変わり、記憶にも残る。行動は直後の結果によって、将来の頻度や強度が変わる。増える場合には強化、減る場合には弱化と呼ぶ。増える場合の結果を好子、減る場合の結果を嫌子と呼ぼう。たいていの子どもにとってはお菓子や親の注目・褒め言葉が好子だし、大人にはお金や地位が好子になるだろう。子どもには苦いコーヒーは嫌子だし、どんな人でも激しい金属音や疼痛は嫌子になるだろう。何が好子か嫌子かは人それぞれである。鎮静薬依存の患者にとってはベンゾジアゼピン系薬物が好子になり、精神刺激剤依存の患者にとってはアンフェタミンが好子になる。大勢の場で拍手喝采と握手を受けるような賞賛や注目は、自己愛性パーソナリティーの人にとっては好子であり、自閉症の人にとっては嫌子である。状況によっても違う。人から注目されることが何よりも好きな人でも、「トイレの個室の中だけは勘弁」と言うだろうし、過食症の人でも食べたくないときはある。
好子や嫌子が単独で提示されることも実験室以外ではありえない。日常生活では人に与えられた行動の選択肢が常に複数あり、一つの行動に随伴する好子や嫌子も複数ある。結果的に何が好子であったか、嫌子であったかは行動を実際に繰り返し観察しなければわからない。大人が子どもの行動を褒めるとき、大人の顔が引きつっていれば嫌子の方が大きくなるときがあるだろう。褒め言葉のタイミングが悪ければ、褒める側の意図とは全く違う行動を強化することにつながる。
生きているもの全てが寝ているか、泥酔しているかでもない限り常に行動している。常に何かに働きかけ、何かの強化と弱化を受けている。たとえばキーボードを叩いてこの文章を入力している私は、画面に現れる文字によって強化されている。もし、叩いている最中に「Wordで問題が発生したために終了する必要があります」と出てきたら、弱化される。今、この文章を読んでいるあなたもそうだ。精神療法を行っている最中の治療者もそうだ。
しかし、私たちは普通、自分が注意を向けている対象にだけ意識が向い、結果が自身に及ぼす影響にまでは目が届かない。「無意識のうちに薬や食べ物に手が出る」「いくら褒めても叱っても相手に伝わらない」と私たちはよく言うが、結局のところ、それは行動の結果やそれから自分が受ける影響を意識していないせいだ。それは昔の私自身にも当てはまる。山上先生から「患者の話をもっと聞け」と叱られたとき、私は「忙しいからそんなに患者の話を聞く暇はありません」と口答えしていたころの私は、“黙って聞く”という努力が自分に与える影響を意識していなかった(原井, 2012) P113。その頃の私は、話が長くなりがちな患者の面接をする時、いかにも嫌そうな“我慢”顔をして話を聞いていたはずだ。言いたいことを我慢し、努力することでそうなってしまうのだが、やっている側はそれに気づかなかった。
そうこうするうちに精神科医として行動療法をするようになって30年がたった。自分がしてきたことを振り返ると、その当時は気づかなかった自分の好子と嫌子が分かってくるようになった。全てを把握するのは無理だが、私の行動を強化する事象、弱化する事象にパターンがあるらしいことはわかってきた。要は好き嫌いのことであり、格好良く言えば価値観のことだ。私の嫌いなことから話を始めよう。
2. 逃避・回避したいこと
定義上、嫌子は避けたいものである。避けるということは、近づいてよく観察したり、考えたりするのも避けるということだから、嫌子の系統的なリストアップは不可能である。他の人の行動と比較したときに、自分が何を避けているかようやくわかるぐらいである。私が他人と比較して気づくものをいくつかピックアップしてみよう。
- 30年前、肥前療養所で働き始めたころ、初発の統合失調症の男性患者の入院を担当したときのことを覚えている。急性幻覚妄想状態だった。ハロペリドールを投与し、数日後には改善し、疎通ができるようになった。患者も家族も私に感謝し、1ヶ月後は退院、2ヶ月後には復職した。良くなったことは確かに良かったし、病棟スタッフも褒めてくれたのだが、私は違和感をもった。薬の処方箋には私のサインがあるが、薬の種類と量を決めたのは当時の病棟医長だった。何か自分で考え、自分で行動し、それで得た結果についてでなければ嫌だと私は思うようである。
最近の認知行動療法のトレンドは治療マニュアルである。マニュアル通りにすることの何が面白いのか、私にはわからない。もし、30年前、行動療法を学び始めた時、もし仮に、山上先生が「マニュアル通りにしなければ、それは行動療法ではない」と叱ったとしたならば、私は行動療法を止めていただろう。創意工夫こそが私にとっての行動療法である。 - 診察中に、相手を褒め倒す患者がいる。治った後で褒めてくれるなら良いが、まだ治ったとはとても思えない時期に医師の好意を買うためかのように褒めてくる。「先生だけが私のことを分かってくれる」「先生がいないと私は生きていけません」「他の先生では駄目」と頼ってくる言葉を聞くと、私はまるで賄賂か何かのように感じる。関心と同情を引きつけるためなのか、問診する側の興味に合わせた症状や過去を語ってくる患者もいる。外では普通に歩いていたのに、診察室では大げさな歩行障害を示す患者もいる。解離症状(転換症状)ということになるのだろう。こうした行動に私は無関心である。紹介状には“解離性同一性障害”と書いてあり、初診時は退行していた患者も、数回目の再来では退行しなくなる。行動療法の言葉で言えば、いくら解離しても、私の注目(好子)を得られないことを経験すると、“解離症状”行動は弱化され(好子消失の弱化)、改善する。
- 行動療法には世界大会がある。1988年のエジンバラ大会から、肥前の行動療法仲間で一緒に行くようになった。忘れもしない、この学会でEdna Foaのワークショップに参加し、ここで私はエクスポージャーにトイレを使うことを知ったのだった。さらに、この学会では私の行動の仕方がちょっと変わっていた。他の仲間は学会場や観光、食事で顔見知り同士一緒に行動していた。自分だけ外れになるとか、外国で一人ぼっちでいるとかは普通の人にとっては嫌なことになるようだったが、私にとってはそうすることが好きだった。国際学会とワークショップにはこのあとも毎回参加するようになったが、往復の飛行機をのぞいてみなと一緒に行動することは少なかった。日本に帰れば嫌でも毎日顔を合わせる相手と海外でも顔を合わせて何が面白いのか?と私は考えていた。私はポジティブな逸脱でありたい(Gawande, 2013a)。
- 私は“癒やし”という言葉が嫌いである。良く目にする“心の傷を癒やす”という表現が嫌いである。それが始まったのがいつからなのかもよくわからない。小学生のとき、体育が下手でからかわれることが多かった。特にダンスがだめだった。周りと同じような京都弁が話せず、口下手で内気だった。そんな自分を変えようと中学・高校では演劇部に入った。スポーツができるようになろうと大学では水泳部に入った。精神科医になってからはエアロビクス・ダンスを始めた。エクスポージャーを知るはるか前から苦手に挑戦していたことになる。精神的な苦しさで言えば今までの一番は、当時小学2年生だった息子が死にたいと言い出したときのことだろう。その間も向き合うようにしていた。ピークが過ぎてからも辛さを忘れることがないよう、日々の様子を日記にしていた。そして、その時の体験を匿名で雑誌Be!に投稿した(匿名, 1999)。今の私は、傷・痛み・苦しみからは逃げず、向き合うべきだと思っていて、そうすることによって得たものが多いことを自分の経験からわかっている。
3. 求めていること
定義上、好子は好きなものである。しかし、私にとっては始めた理由が“好きだから”というものがあまりない。医者が好きで医学部に進んだわけではない。精神科が好きで進んだわけでもない。水泳部では幼児のころからスイミングスクールに通っていた同級生にラップされていた。エアロビクスも好きで始めたわけではない。私の踊りのセンスは最悪である。肥前療養所の盆踊りではたいてい笑われ、「エアロが趣味です」と言うともっと笑われた。それでもブリジストン・スポーツクラブからYMCA、ルネサンスと30年、欠かさず続けている。おそらく私は嫌なこと・苦手なことをあえてやって慣れていくのが好きなのだ。そのためにいろいろ工夫するのが好きなのだ。
しかし、もちろん嫌なことばかりでは“続ける理由”としては不足している。30年もエクスポージャーをやっていれば、嫌なことも減ってくる。人前で話すことは今では私にとって好きなことに変わり、内気そうに黙っている方が苦手になってしまった。30年間、私が行動療法を“続ける理由”になった好子について、治療した患者さんたちが残してくれた手紙や体験談などから探してみよう。
30年前、担当した双極性障害の患者が今もセルフモニタリングを続けていた!
初診時21歳の女性である。躁状態の極期には隔離室が必要だった。年に4回以上のエピソードがあり、急速交代型と診断できた。セルフモニタリングを通じて躁状態の前兆に本人が自分で気づくようにし、早期に抗精神病薬を増量できるようにした。その結果、入院を防ぐことができるようになったと考え、論文にしている(原井, 1997)。それから、約30年後、私も2回転職した。2016年の夏、患者に再会するチャンスがあった。患者は、服薬はもちろんセルフモニタリングを今も続け、睡眠時間などの日常生活を安定させることを怠っていなかった。許可を得て患者からの手紙の一部を示す。
私は先生をはじめとしてスタッフの方に良くしていただきました。もし,病気になっていなかったなら,肥前には来ていないし,先生にもお会いしていません。傲慢で何もわからない人間になっていたんじゃないかと思います。
先生が以前に私に「あなたは、幸か不幸か、病気になったわけだから」とおっしゃいました。本当に幸か不幸かと思います。心の持ち方で決まるのではないかと思います。
私が書いた感想文(入院当時に書いてもらったもの)は公開されてかまいません。
私も先生と同じで病気で悩む方に役立てれば良いと思います。
当時20代だった私が、そんな偉そうなことを言ったとは信じられない。たとえ言ったとしても押し付けるばかりで、患者に納得させられるような話術は持たなかったはずだ。しかし、患者は見事に双極性障害をアクセプトしており、病気を忌むべきものとせず、むしろ良い経験になったとしている。ACTが日本に入る前から、この患者はアクセプタンスができていたのだった。30年後に、このことを知ったときの私の驚きを想像してほしい。詳しくは私のブログに書いている。
http://hharai.cocolog-nifty.com/choice/2016/10/y-7b95.html
とらわれからの自由 No.1~10に驚かされる
臨床家としての私に影響を与えたものに依存症の臨床がある。一時は断酒会やAA(Alcoholics Anonymous)、NA(Narcotics Anonymous)に毎週のように通っていた。そこで知ったことは回復者が語る体験談の強さだった。私も真似をして、エクスポージャーを行って強迫症や不安症を乗り越えた患者に対して、治療体験談を書いてもらうようにした。それを次の新しい患者に読んでもらうことで、私が下手な面接をするよりも-そのころは動機づけ面接を知らなかった-はるかに効果的なエクスポージャーに対する動機づけになった。エクスポージャーは“嫌なことをわざと進んでやろう”が基本である。“やりたくない”と患者が嫌がるのが当然である。私のような嫌だからやってみるという人間は変わっている。そうした嫌がる患者も、先輩の患者が迷いに迷った後、エクスポージャーにチャレンジし、強迫を乗り越えた喜びを語る体験談を読むと顔色が変わった。毎年、何人、何十人もの患者を治療するうちに、体験談も多数になった。A4用紙にプリントしたものから、小冊子にしようということになった。それが「とらわれからの自由」である。患者・家族のサポートグループであるOCDの会から、第1号が出版されたのが、2005年12月である。2016年12月に第10号が出版された。
第10号の巻頭言を書くとき、1~9号を読み直した。改めて患者の変化と成長に目を奪われた。加害恐怖に苦しんでいた30代の主婦は私が熊本にいた頃から行動療法を開始し、名古屋でも治療を継続した。この間に二人目の命を授かった。最初は薬無しのERPだけで強迫を乗り越え、子どもも授かったものの、子育てが始まってからまた新しい強迫観念に悩まされることになった。結局、SSRIの維持服用を選ばざるを得なくなった。飲んでいないときには思考のキレ・冴えのようなものがあり、薬によってそれを失うのが嫌だと言っていたが、そのキレ・冴えは強迫観念の源泉でもあった。23年間強迫に苦しんでいた40代女性は、一回目の3日間集団集中治療だけで終わらず、2回受け、その後も個人カウンセリングを数年続けた。この間に親元から自立したり、転居したり、犬を飼ったりしている。体験談も3回書いてくれた。最初は自分を守って欲しいといつも誰かに頼っていた弱い人だったが、最後には自分よりも弱い生き物-子犬-を守ろうとする強い人になった。
とらわれからの自由はOCDの会のサイトから注文できる。
http://ocdnokai.web.fc2.com/kounyu.htm
行動療法研究の査読者として驚かされる
学会誌の査読は面倒がかかるばかりで、自分にとって益になるものがない、と思う人が多いだろう。行動療法研究の副編集委員長・編集委員長を合計12年間やってきた私もおおよそ同意する。しかし、例外はある。行動療法研究第42巻3号はACTの事例研究の特集号である。そのうちの一つの論文(小川, 2016)から一部を引用する。
スーパーパイザーとしての査読者-原井(2016)へのリプライ-
以下に原井(原井, 2016)でも取り上げられた、著者の観察不足に関するアジェンダについて述べてみたい。この症例では著者はマニュアルや教科書などのお手本に囚われてしまい、クライエントを観察しそこから得られた所見の記録が不足していた。人間の注意機能は有限なので、マニュアルを遵守できているかということに注意が向けばそのほかの要素に向ける余裕がなくなることになる。もちろん原井(2016) が指摘するように、ここではクライエントと治療者の聞で起こる行動随伴性をマインドフルに観察できることが重要である。
審査者からのアドバイスとして、たとえばこんな感じで観察内容については記載できるのではないか、とコメントがあった。
「査読者による勝手な想像だが、1回目での様子はこんな患者なのではないだろうか?
記載例 中肉中背でとても健康的に見える女性。腰痛の既往があるが診察室の椅子には背筋を伸ばしてまっすぐに腰掛け、何も支障があるようには見えない。入室時や退室時には目を合わせてきちんと挨拶をし、そわそわしたり、確認したりするなど緊張や不安を思わせるそぶりがない。呼び出してから入室するまでに時間がかかることから、待合室では人の少ない、離れた所に座っていた可能性がある。きちんと化粧し、年齢よりも若々しい。酒落たブラウスを着ており、身なりが整っている。自分から積極的に話し、内容にまとまりがある。やや視線は固定気味で、隣の部屋で物音がしてもそちらに視線が向くことはない。人前では「汗が出たり、喉が渇いたりする」と訴えるが、外見的にはそのようなことはない。表情が微笑のまま固まっているようで、話のテーマが辛さや苦しさに及んでも、喜怒哀楽の表情が表にでることがない。」
もちろんこの記載がクライエントその人を完墜に再現しているわけではないが、かなりの程度審査者が推測したとおりと言える。個人情報の関係もあるので個々の相違点などは申し上げられないが、想像でここまで当てることができるのかということに驚嘆した箇所は複数ある。
査読の過程は投稿者の臨床で何が起こっているのかを推測する営みである。自分に何が分かっているかは自分ではわからない。だから、こうやって査読した相手から○をもらえたことは素晴らしい経験だった。投稿論文だけを元にして、一度も見たこともないクライエントの様子を想像だけで言語化することについて、私は今になって自信をもてたわけである。コツや勘所を教えてもらえればできるようなものではない。普段から、患者をよく観察し、その結果を記録にすることを繰り返していなければできるようにはならない。そして、どんな治療法の専門家でも、たとえ行動療法を毛嫌いする人であったとしても、観察と記録の大切さには同意してくれるだろう。
知的興味を満たしてくれる
30年前は、たいていの精神療法家は行動療法を評して「人を実験動物扱いしている」「ラットの実験結果を豊かな思考を持つ人間に当てはめてもうまくいくはずがない」と言っていた。実際に私が行動療法を学びだした頃は、行動主義とはワトソンのいう行動主義のことであり、“心”はブラックボックスであり、ウィトゲンシュタインが言うように「語りえないものについては、沈黙しなければならない」になっていた。知り合いの実験心理学の研究者も言語や思考について触れるのを避けていた。行動・情動は行動療法で、心・言語は認知療法で、のような役割分担が暗黙の了解だった。
今は違う。学習理論の進歩は凄まじい。言語はもはや人間の専売特許ではない(松沢哲郎, 1989)。数字の記憶能力ならばチンパンジーの方が大学生よりも上である(松沢, 2008)。スキナーの弟子であるRichard Herrnsteinが発見したマッチング法則が行動経済学につながり、それをDaniel Kahnemanの本(Kahneman, 2011)で学ぶことができる。刺激等価性の発見が言語を行動から捉えることを行動分析家にとってのホットなテーマにした(武藤, 2014)。薬物の反応ももちろん行動で解釈できる。行動薬理学に関する本を私も書いた(原井宏明, 2012)。行動療法に触れなければ、ここまでわくわくするような知的興奮は得られなかっただろう。
アメリカ人外科医の本に驚かされる
2013年にAtul Gawandeの本を訳出した(Gawande, 2013b)。2016年に2冊目、「死すべき定め」を出した(Gawande, 2016)。依存症の臨床以外に私の臨床に影響を与えたものをもう一つあげろといわれればこの2冊の本を上げる。その一例をあげよう。「死すべき定め」の第8章「勇気」ではGawandeはこう述べる;
老いと病いにあっては,少なくとも2種類の勇気が必要である。一つ目は,死すべき定めという現実に向き合う勇気だ-何を恐れ,何に望みを持つかについての真実を探し求める勇気である。この勇気は難しく,持てないのも当然だ。真実から目を背けたい理由はいくらでもある。しかし,さらにもっと厳しいのは二つ目の勇気だ-得た真実に則って行動する勇気である。何が賢明な道なのかはしばしば曖昧であり,それが人を悩ませる。長い間、私はそれを不確実性のせいだと単純に考えていた。この先の予測が難しければ,何をすべきかを決めるのが難しくなる。しかし、いろいろ経験するうちに,本当のハードルは不確実性さよりももっと根本的なことだと気づいた。恐れか望みか,どちらが自分にとって最も大事なことなのかを決めなければならないのだ。
このあと、GawandeはDaniel Kahnemanから引用し、“脳は苦しみのような経験を二つの方法で評価する―経験を起きている瞬間に理解することとその経験を後から見直すこと―そしてこの二つの方法は根本的に相互矛盾する”と論じ、ピーク・エンドの法則を説明する。
セルフモニタリングと動機づけ面接に続く、行動療法の勘所の3つ目を上げろと言われれば、私は迷わずエクスポージャーを挙げる。山上先生から学んだのは、不安階層表を作り、楽なところからエクスポージャーを開始し、徐々に刺激の強度を上げていくことだった。常識的に見えるし、たいていの行動療法家もそうしている。しかし、私は徐々に不安階層表を無視するようになり、今はまったく使っていない。可能ならば最初のセッションで最強度の刺激を使ってエクスポージャーをするようになった。山上先生なら「患者がどうなるのかを予測できないのに、無理なことをするのは駄目」と怒るところだ。私には「結果が出るからそうしています」以外の答えがなかった。
「死すべき定め」を読んでから、最初に強い刺激を持って来たほうがなぜうまくいくのか、患者がエクスポージャーをなぜ自発的にするようになるのか、その理由をピーク・エンドの法則で説明できることに気づいた。人間は不安の体験の総量を記憶しない。どれだけ不安の総量が多かったとしても、時間も長かったしても、不安のピークと終わりの時のレベルだけを記憶していて、終わりが下がっていれば「良かった、またやれる」になる。逆に、いくら不安の総量が少なく、時間も短かかったとしても、終わりのレベルがちょっとでも上がっていれば「嫌だった、もうやりたくない」になる。やる前は不安の総量に対して慄くが、終わってしまえば「思ったほど大したことなかった」になってしまう。そしてピークとエンドの対比が大きければ大きいほど、期待と結果の違いのズレが大きければ大きいほど、次もやれるという自信になる。
外科医が書いた終末期医療の本から、エクスポージャーのヒントが得られると思う人はいるだろうか?
III. あなたはどうなりたいのか?
1. 行動療法には理想はない
理念型としても口癖としても“理想の行動療法”、“究極の行動療法家”というものはない。30年前、行動療法を学び始めた頃、そのことを行動療法の欠点だと思っていた。エリクソニアンやフロイディアンなら、それぞれエリクソン・フロイドに帰れ、原点に帰れという話になるだろうが、行動療法には帰るところはない。似たような言葉にスキナリアンがあるが、スキナーはそもそも治療者ではないから、精神療法の文脈で“スキナーに帰れ”と言い出すような人はいない。行動療法そのものが常に変化している。患者の中には特定の病気に悩んでいるというよりも、この先の自分の人生をどうしたらいいのかわからないので悩む、生きる上での指針が欲しいと訴えて受診する人がいる。強迫や不安を改善させたところで、人生の指針が見つかるわけではない。“人はこう生きるべきだ!”は普通は押しつけがましいが、将来の目標を持てないと訴える患者はそれを欲している。こういう時、行動療法はどう使うのだろう?
私の場合の逃避・回避したいこと、求めていることを先ほど書いた。今の私は、30、20年前の私の考えの中で間違っていたものがあることを知っている。もし、昔の自分に会えるとしたら、いろいろ教えてやりたいこともある。30年後には行動療法の専門家として認められ、原稿依頼が来るようになる、訳書の一つはベストセラーの一角を飾るようになり、大学生になった娘が大学の書籍売り場で平積みになっていることを嬉しそうに報告してくれる、と伝えてもやりたい。もっとも、そんなことしたら30、40歳の私は“余計なお世話だ”と嫌がるだろう。息子のことで悩んでいる時なら、“何の縁があって死についての本を翻訳しなければならないのか?そんな暇があるなら、本来の自分の仕事をする”と言うかもしれない。それでもこうやって30年間を振り返ると、私が避けたいこと、求めていること、“価値観”は変わっていないことに気付く。その時その時の判断を後から見れば間違っていたものがたくさんある。しかし、その時にはそれで完全だったのだ。
読者のあなたにとってはどうだろうか?何を避け、何を求めるのだろう?完全はない。だからこそ工夫のしがいがある。
2. 機能的文脈主義
ここまで私が書いてきたことが機能的文脈主義である。実用主義と機能主義、文脈主義をあわせた現代哲学の一つだ。スキナーの徹底行動主義の延長線にあり、操作可能な環境要因と行動を用いて、行動を予測し、制御することを目標に置いている。行動の範囲は拡張され、言語や思考、情動など生物に可能なことすべてを含んでいる。ACTはこの主義を明示的に採用している。
あなたはどんな哲学を持っているだろうか?フッサール、ウィトゲンシュタインと聞いてうんざりしてしまった人でも、世界観ぐらいはもっているだろう。次のイエス・ノー質問を考えることで、あなたの哲学を分類してみよう(Pepper, 1942)(武藤, 2001)。
- 世界は要素で構成されていて、究極の要素に還元して観察し、判断することが原理としては可能である イエス・ノー
これは世界が素粒子から構成されているか?精神状態は個々の神経伝達物質の働き・無意識の働きに還元できるか?精神疾患の完全な分類はあるのか?統合失調症の原因となる究極の精神病理はあるのか?という質問と同等である。究極の大和魂はあるのか?でも良い。
ちなみに私はノーである。自分自身の行動療法の要素を数個程度にまとめることすらできないのに、世界や精神状態を有限の要素にまとめられるはずがない。現在一応の主流の“要素”はあるが、それもとりあえずそうしておくのが便宜上は好都合だから、文句が出ないからという関係者側の都合によるものだけである。 - 世界は意味がつながった単一のストーリーになっている。だから、一見、支離滅裂に見えるものでも隠された何かを探しだして一つのストーリーに紡ぐことが可能である イエス・ノー
もし、聖書は真実の書だと信じるなら、世界は創世記から始まり、最後の審判で終わる。あなたが敬虔な一神教(ユダヤ、キリスト、イスラム)あるいは一部の仏教(浄土信仰など)の信者ならば、未来の救いを信じているのだから、イエスと答えることになる。逆に、聖書やお経は単なるお話し・儀式としか思わないし、神や浄土の存在は手前勝手にそうだと想像しているだけで嘘か本当かは死ぬまでわからない、親鸞に騙されたという結果になっても恨まない、そもそも死んだらと恨みようがない、と言うならばノーである。
生物進化に置き換えても良い。「創世記は古事記と同じく神話、進化は事実」と考える人でも、もし、細菌から虫、人まで、生物は複雑かつ高度で、優れた方向に進化してきたと考えるならばイエスである。ネオ・ダーウィニズムの立場、すなわち、進化は一方向性ではなく、大腸菌もゴキブリも人も、それぞれが等しく高度であり、環境に適応しており、(ヒトの一本の腸にいる腸内細菌は約3万種類、1000兆個、約2kg、昆虫は80万種以上で現在知られている生物種の半分以上を占めるが霊長類は220種しかいない)、なぜこうなったかはランダムな変異と系統的な自然選択の産物であり、決まったストーリーはない(私の行動療法の変遷も同じだ)と考えるならば、ノーである。
1,2のいずれに対してもノーと答えるのが文脈主義である。一方、イエスと答える哲学の代表選手が論理実証主義(Logical Positivism)である。論理経験主義(Logical Empiricism)、科学経験主義とも呼ばれる。この立場は少数の原理から、全ての複雑な事象を論理的に説明できると考える。逆にすれば、どんな複雑に見える理論であっても、少数の命題に論理的に分解できるという意味である。そして、その理論のなかから、実験や観察によって実証されていない命題を発見できたら、その理論の全ては机上の空論であると判断する。数学的な公理体系に実証主義を加えたものだ。もし、あなたが神経生化学の研究者やメタアナリシスを専門にする臨床疫学研究者だったら、論理実証主義を当然として受け入れているのではないだろうか?
機能主義はいままでに何度か触れてきた。繰り返しになるが、物事を認識するとき、それがもたらす結果、“機能”で認識しようというやり方である。心も特別扱いしない。普通の人はチンパンジーが言葉を綴っても、チンパンジーに知能がある、心があるとは思わないだろう。コンピューターに心があるとは常識では言わない。しかし、グーグル社が開発したアルファ碁について、元・女流本因坊の小川誠子六段が次のように述べている。
「アルファ碁の強さに驚きました。中盤から後半がとくにしっかりしています。コンピューターなのに、感情が入っている気がしたくらいで、李九段とは人間同士の碁のように楽しみました。」
http://ironna.jp/article/3126?p=2
機能主義から言えば、これは当然のことになる。コンピューターには感情が入っている。しかし、あくまで碁で対戦しているときだけのことだ。与えられた文脈で目標があるから、すなわち世界トップの棋士と連戦し、相手の弱みを見つけて勝て、という設定があるから、感情が入っているようにみえる。
機能的文脈主義では、どうすれば勝ったことになるのか、何連戦するのか、そのようなゴールを一人一人が自分の置かれた文脈に基づいて、自分で恣意的に決めなければならない。私の場合は何かを乗り越えるために工夫し、その後で意外な発見をすることだった。山上先生との軋轢が生じてもそうしていた。患者にセルフモニタリングをさせ、治療体験談を書いてもらうという習慣がそのための道具になった。
IV. 読者に問う
読者はどうだろうか?何を求めて仕事をするのだろう?何を避けて仕事をするのだろう?
あなたの哲学は次の質問にどう答えるだろうか?
1.世界は要素で構成されている
2.世界は意味がつながった単一のストーリーになっている
そして、何をゴールにするのだろう?30年後についてはどうなっていればよいと思うのだろうか?自分が専門にしている領域は?自分自身については?最後にそのためには15ある精神療法のどれを選び取るのだろうか?
ちなみに私は1,2にはノーと答える。無神論者であり、死後の世界があるとは信じない。同じように精神疾患の完全な分類があるとは思っていないし、精神療法の分類に興味がない。全ての謎を科学的な実証研究で解き明かすのは原理的に不可能だと思っている。しかし、宗教美術は好きで、中高で学んだ聖歌は今でも口ずさむ。どの宗教でも天国や極楽は陳腐なワンパターンなのに、地獄は限りない多様性があって面白い。科学雑誌は昔から好きで今でも面白いし、科学の営みとは謎を減らすことではなく、増やすことだと思っている。
V. おわりに
この小論を書くために随分勉強した。哲学書を開くのは何年ぶりかだ。ふと、気づいて私の昔の日記を開いてみた。
1977/4/23 原井哲学の終着点
真理はない 一定の仮定に基づく論理的法則体系があるのみ たまたまそれが現実の事象と似ているように認識される。
これを書いたのは40年前だ。人生と勉強は何年やっても面白い。自分の日記(セルフモニタリング)からも驚きが得られる。
文献
Bellack, A. S., Hersen, M., & 山上敏子. (1987). 行動療法事典. 岩崎学術出版社.
Fernando, C. T., Liekens, A. M. L., Bingle, L. E. H., Beck, C., Lenser, T., Stekel, D. J., & Rowe, J. E. (n.d.). Molecular circuits for associative learning in single-celled organisms. http://doi.org/10.1098/rsif.2008.0344
Gawande, A. (2013a). パフォーマンス. In 医師は最善を尽くしているか (pp. 212–227). 東京: みすず書房.
Gawande, A. (2013b). 医師は最善を尽くしているか 医療現場の常識を変えた11のエピソード. (原井宏明, Trans.). 東京: みすず書房.
Gawande, A. (2016). 死すべき定め―死にゆく人に何ができるか. 東京: みすず書房.
Georgopoulou, S., Prothero, L., Lempp, H., Galloway, J., & Sturt, J. (2015). Motivational interviewing: relevance in the treatment of rheumatoid arthritis? Rheumatology (Oxford, England). http://doi.org/10.1093/rheumatology/kev379
Hays C., S., & Smith, S. (2010). ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)をはじめる セルフヘルプのためのワークブック. (武藤崇, 原井宏明, 吉岡昌子, & 岡嶋美代, Trans.). 東京: 星和書店.
Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. (村井章子, Trans.). 早川書房.
Pepper, S. C. (1942). World Hypotheses: A study of evidence. Berkley, Los Angels and London: University of California Press.
原井宏明. (1997). 急速交代型双極性障害に対するセルフモニタリングと薬物自己投与による躁病再発予防の試み. 精神医学(0488-1281).
原井宏明. (2012). うつ・不安・不眠の薬の減らし方. 東京: 秀和システム.
原井宏明. (2012). 方法としての動機づけ面接. 東京: 岩崎学術出版.
原井宏明. (2016). ACTは普及するのか?技術普及のプロセスで起こること-小川(2016)へのコメント-. 行動療法研究, 42(3), 323–325.
小川成. (2016). スーパーバイザーとしての査読者-原井(2016)へのリプライ. 行動療法研究, 42(3), 327–329.
松沢哲郎. (1989). ことばをおぼえたチンパンジー. 東京: 福音館書店.
松沢哲郎. (2008). 直観像記憶と言語のトレードオフ仮説 連載ちびっこチンパンジー第74回. 岩波書店「科学」, 78(2).
松尾正. (1986). 分裂病者との間で治療者自身が沈黙するとき,そこにもたらされるもの 現象学的治療論の一試み. 精神神経学雑誌, 88(8), 509–538. 原著論文.
匿名. (1999). 《ある精神科医の記録》息子のうつ病につきあう<1>. 季刊アルコールシンドローム&Be!, (56), 48–49.
武藤崇. (2001). 行動分析学と「質的分析」(現状の課題). 立命館人間科学研究, 2, 33–42.
武藤崇. (2014). アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT) 行動分析学の「伝統と革新」の結実. 精神療法, 40(1), 60–63.
Bellack, A. S., Hersen, M., & 山上敏子. (1987). 行動療法事典. 岩崎学術出版社.
Gawande, A. (2016). 死すべき定め―死にゆく人に何ができるか. 東京: みすず書房.
Georgopoulou, S., Prothero, L., Lempp, H., Galloway, J., & Sturt, J. (2015). Motivational interviewing: relevance in the treatment of rheumatoid arthritis? Rheumatology (Oxford, England).
Hays C., S., & Smith, S. (2010). ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)をはじめる セルフヘルプのためのワークブック. (武藤崇, 原井宏明, 吉岡昌子, & 岡嶋美代, Trans.). 東京: 星和書店.
Pepper, S. C. (1942). World Hypotheses: A study of evidence. Berkley, Los Angels and London: University of California Press.
Richardson-Jones, J. W., Craige, C. P., Guiard, B. P., Stephen, A., Metzger, K. L., Kung, H. F., … Leonardo, E. D. (2010). 5-HT1A autoreceptor levels determine vulnerability to stress and response to antidepressants. Neuron, 65(1), 40–52.
奥田健次. (2012). メリットの法則 -行動分析学・実践編. 集英社新書. 東京: 集英社.
原井宏明. (1997). 急速交代型双極性障害に対するセルフモニタリングと薬物自己投与による躁病再発予防の試み. 精神医学(0488-1281).
原井宏明. (2012). 方法としての動機づけ面接. 東京: 岩崎学術出版.
原井宏明. (2015). 強迫性障害の認知行動療法-個人療法,集団集中治療,サポートグループ. In 原田誠一 (Ed.), メンタルクリニックが切り拓く新しい臨床 (pp. 99–108). 東京: 中山書店.
原井宏明. (2016). ACTは普及するのか?技術普及のプロセスで起こること-小川(2016)へのコメント-. 行動療法研究, 42(3), 323–325.
小川成. (2016). スーパーバイザーとしての査読者-原井(2016)へのリプライ. 行動療法研究, 42(3), 327–329.
武藤崇. (2001). 行動分析学と「質的分析」(現状の課題). 立命館人間科学研究, 2, 33–42.