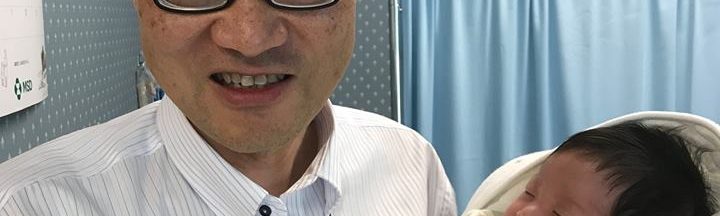注意 この原稿は草稿です。最終版ではありません。引用などはお控え下さい。
I. ある二分法:診断はパズルかミステリーか?
診断はいわば一種の謎解きである。そして謎はパズルとミステリーの2つに分けられる。前者はどんなに複雑怪奇に見えたとしても正解は一つだけだ。30年前の知人が今も生きているか死んでいるかは答えが一つしかない。診断でいえば,たとえば脳腫瘍が原因になって生じた精神症状であればその腫瘍を見つけ出すことが診断のゴールである。多種の腫瘍が同時に生じる(重複癌)は例外的だから,一つ見つければ良い。所見や病歴などあらゆる情報を集め,検査し,まだ見つかっていない何か一つを発見することに注力することになる。情報は多ければ多いほど良い。診断上手な医者とは必要最小限の情報で正解に到達できる人のことである。診断の凡人でも情報を集めることさえ怠らなければ,いつかは正しい診断に到達する。一番悪いのは情報集めを怠り,見落とす医者だ。
逆に,ミステリーは調べれば調べるほど迷宮に迷い込み,判断に自信を持てなくなるような謎だ。知人の30年間の人生が幸せだったか不幸だったかはどう決めればいいだろう?再会した瞬間に幸せそうかどうかは判断できるだろう。しかし,30年間の話を微に入り細に入り詳しく聞いたとしたらどうなるだろうか?私は精神科医を続けて30年になる。診た患者の数は数千人を超える。その中には本一冊でも足りないような壮絶な人生を経てきた患者がいる。診断基準を当てはめただけでも,うつ病やPTSD,パニック症,社交不安,アルコール・睡眠薬依存がつく。アダルトチルドレンやDV,空きの巣症候群などともつけたくなる。そして情報を集めれば集めるほど,その人に何がもっとも良いことなのか,援助するとはどういうことなのかがわからなくなる。これがミステリーである。診断上手な医者とは情報の解釈に長けて実際の援助につなげられる人だ。凡人は間違った診断であっても適当なところで見切りをつけて前に進める人だ。一番悪いのは情報収集癖である。次々情報や検査を加えては新しい異常を発見する。得られた情報をどう解釈したら良いのかわからず,さらに精査する。この間,患者への援助はないがしろにされる。
さて精神科診断はパズルか,ミステリーかどちらであるべきなのだろうか?パズルかミステリー,このような二分法は議論を始める時には必ず必要だ。分類は医学の出発点である。正常と異常を分けなければ、誰が医者か患者かも分からない。一方,二分法は私たちの自由な発想を邪魔する落とし穴にもなる。私もはまっていた。そして落とし穴が恐ろしいのは出てからでないと入っていたことにすら気づかないところだ。一生入ったままの人もいるだろう。まず、私も入っていたうつ病の二分法の落とし穴を掘り返すことから話をはじめよう。
II. うつ病は内因性/非内因性(心因性・神経症性)に二分すべきか?
誰でも素朴に考えれば、心の病気を人間関係や環境など患者の外側に原因があるものと、脳や神経のように患者の内側に原因があるものに二分する。落ち込みと意欲低下、体調不良が長く続き,思い当たるような持病や体の異常がなければ普通の人ならうつ病を考えるだろう。駅前にあるメンタルクリニックに自分で電話をかけて初診を予約し,1週間後に1人で歩いてこれる患者ならば脳腫瘍などはほぼ考えなくてもよい。このような場合,伝統的な精神医学は症状に基づいて内因性と非内因性(心因性・神経症性)に二分する。一方,DSM-III以降、少なくともアカデミックな精神医学の診断分類からはこの二分法は日陰に押しやられている。私は行動療法家だが、診断に関しては感情障害長期経過追跡研究(原井宏明, 1999)で一緒に仕事をした(指導を受けた)古川壽亮先生に多大な影響を受けている。彼の診断学の本から引用する(古川 & 神庭, 2003) P279。
内因性/神経症性の区分にまつわる論争は,イギリスでは一元論のLondon学派と二元論のNewcastle学派との論争として, 50年以上にわたって続いていたものである. 1960年代から1970年代にかけて一連の論文でNewcastle学派のRothらは,内因性うつ病と神経症性うつ病とは別個の疾患であることを証明しようとした。区分が妥当であることを証明するためには,両者が混在した状態が比較的まれであること,つまり「黒Jと「白Jに比して「灰色Jが少ないことを示さなくてはならない.そこで,彼らは129例の内因性もしくは神経症性うつ病の患者の症状評価を重回帰分析したところ,その結果はー峰性ではなく二峰性の分布を示したというのである。しかしながら,後続の研究はそのほとんどがこの結果を追試することに失敗した。現在では, したがって,うつ病の症状は連続的なものでいわゆる内因性と神経症性の症状はそれぞれの純粋形よりも混合形のほうが多いことが認められている。
(中略)
さらに,上述の「うつ病の精神生物学に関する共同研究Jで5年間の追跡期間中に2回以上の抑うつ病相のあった201例の症例を検討したところ,同一症例で内因性に関して一貫した症状が反復される傾向はみられなかった。
これだけのデータにかかわらず,多くの精神科医は,種々の症候,重症度と転帰を示すうつ病すべてをひとからげにすることに躊躇するようである。これが, (薬物によく反応するという神話に加えて)いわゆる内因性うつ病の概念が,多くの研究でその妥当性を確認されていないにもかかわらず,生き残っている理由の1つであろう。しかし,神経症性うつ病については,全くその限りではなく,したがって,もはや時代遅れのものと考えなくてはならない。
もともとの私は他の精神科医と同じで,笠原-木村のうつ状態分類・キールホルツの分類法などの常識を信じていた。落とし穴に入っていたのだ。古川先生に会ったことが穴から出るきっかけになった。診療上の疑問が生じたらコクラン共同計画やUpToDate®を見るようになった。精神病理学の権威が伝統に基いて主張することをまず疑うようになった。
私の懐疑心に拍車をかけたのは、抗うつ薬のプラセボ対照二重盲検ランダム化比較試験(Randomized Clinical Trial, RCT)の経験である。現在,日本で上市されている抗うつ薬の臨床試験の大半に関わった。対照群に対して優越性を示せず闇に消えた薬も数種は知っている。私がプラセボを与えた患者は20人を超える。最初のころは副作用が出たり,反応が早かったりすれば実薬だと思い込んでいた。目の前の患者に飲ませている薬が本当は何なのかは誰にもわからないとは信じられなかった。症例記録を固定するたびに、この患者はプラセボだ、実薬だという賭を治験チームでやってみた。結果は無残だった。様々な薬で何回やってもどの患者がどの群に割り当てられたか誰にも当てられなかった。まさしくランダムだった。やればやるほど明確になったのは治療者・研究者自身が無意識に抱えている思い込み“認知バイアス”を打ち砕く方法としてRCTほどデザインが簡単で強力なものはないという事実だった。一方、治験の依頼者からは「プラセボ反応しやすい患者と、そうではない患者を事前に見分ける方法を教えて欲しい」と何度も頼まれた。私は「できないものはできない、できると答えている研究者は全員疑似科学者だ」と何度も答えた。内因性うつ病は薬に反応しやすいというのはまさしく神話である。何度否定されても不死鳥のように蘇る。うつ病患者に対するプラセボ対照試験は非倫理的だと主張する医師もいまだにいる。
私が自分の診断と治療に対して謙虚であるとすれば、それは行動療法家だからではない。EBMを学び,予測不能なプラセボ反応をRCTの中で繰り返し経験しているからである。それでも症状で病気を分類しようという試みは素人はもちろん,精神科医・行動療法家の中でもなくならない。たとえば私が専門にする強迫症の場合,広汎性発達障害を併発しているならば行動療法は適応ではない,と堂々と主張する専門家がいる。広汎性発達障害に対して応用行動分析のエビデンス(Reichow, Barton, Boyd, & Hume, 2012)があるのを知らないのか?と言いたくなる。しかし,これもまた“内因性うつ病は薬に反応する”神話と同じで,発達障害の有無による二分法の罠から出られないためだろう。
私にもうつや不安症、強迫症を症状で下位分類したらどうだろうか,治療反応性を予測できるのではないかと思っていた時期があった。現在のような境地に至るまでの私個人の“診断学”の歴史を振り返ってみよう。
III. 1980年代:神戸大学精神科研修医
精神科医自体の中での診断に対する態度は様々だ。EBM派/非EBM派と二分することもできるが、同じ人間でも時代・状況によってすることが違う。そして私の研修医時代にはEBMという概念がなかった。
1985~6年,中井久夫教授が率いる神戸大学精神科での研修中に退院まで担当した患者は計21名だった。当時の退院時要約をみると、主診断が精神分裂病(現在の統合失調症)が6人、非定型精神病が4人、アルコール関連が3人、双極性障害(躁状態)が2人だった。他はうつ病や頭部外傷後遺症、心因性反応、解離性障害などが1人ずつあった。全体の20%が非定型精神病だった。言うまでもないが診断はオーベンの指導による。当時の神戸大では満田の非定型精神病(満田, 1968)が流行していた。精神医学のテストで三大精神病とは何か?と聞かれたら、精神分裂病と躁うつ病、てんかんと答えるのが正解の時代だった。
精神衛生法の時代である。もっともよく使う入院形式は“同意入院”だった。患者本人の同意ではなく,保護義務者の同意だ。精神分裂病でもうつ病でも病名を患者に告知することはありえなかった。患者が見る可能性がある診断書には「神経衰弱」「心身症」と書いた。心理教育という概念はなく必要もなかった。患者には知らせないし、診断書には偽りと分かっている当たり障りない病名を書くからだ。そして何よりも仮に正しい診断をしたからといって何か患者にとってプラスになることができそうにはなかった。抗精神病薬の効果は明らかで急性幻覚妄想状態であればほぼ確実に治せていた。ベゲタミンを出して夜は静かに眠らせることもできた。しかし、それ以外はどうしたらいいかわからなかった。心因性ならば精神療法をすることになっていたが、何にどういう精神療法が有効なのかは教科書になかった。強迫神経症は難治性疾患の代表で、どんな薬でも誰が精神療法をしても治らないことになっていた。研修医に配られた中井先生の本には強迫症は“うす紙をはぐように消えていく。周囲がそれを話題にするとかかえって強まる。無理に止めると不安が起こる。周囲は一つのクセと考えている方がよい。”とあった(青木, 遠藤, & 中井, 1984)。これは治し方ではなく、付き合い方だった。
治らないことが初期設定であり、心理教育の必要もない。だから、“同意入院”させる必要があるかどうかだけが大切で、それ以外は細かな診断にこだわる理由がなかった。一方,当時の神戸大学精神科には神経内科医も同居していた。神戸大では神経内科はまだ独立していなかった。そのせいか、研修医の教育では器質的な背景を見つけ出すことが重んじられた。神戸大学時代の21人のうち、7人に器質的・物質的な背景の診断があるのはそのせいである。神経学的検査と脳波検査、髄液検査は研修医にとってのルーチンだった。X線頭部CTが導入されたばかりである。画像検査に頼る前にまず自分の目と手で見つけなければなかった。
精神科診断と神経内科診断は天と地のように違う。ウェルニッケ脳症やターナー症候群、正常圧水頭症など丁寧に情報を集めることでパズルを解くように答えをだせた。脳に興味がある仲間のうちで診断をパズルにしたい者は神経内科、ミステリーで十分と思う者は精神科を選んだように思う。精神科医を目指す者は白衣ではなく平服を着ていた。助教授の山口直彦先生は外来診察室で患者は座らせたまま、自分はベッドに横になっていた。中井教授は大名行列のような教授回診が嫌いだった。誰が患者か医者なのかさえ外から来た人間にとってはミステリーだったのである。
IV. 行動療法家になり始めた頃:第一世代の行動療法
私が研修医だった時、すでに行動療法は世にあった。神戸大学を含むほとんどの精神医学教室の中になかっただけである。強迫症に有用であることもごく一部の人にはわかっていた(浜副, 1985)。認知行動療法の名前はまだない。後世の人はこのころの行動療法を“第一世代”と呼んでいる。
精神療法の流派はたいてい治療理論だけでなく、それに一致した病理理論を持っている。精神分析ならエディプス・コンプレックス、森田療法なら森田神経質、アドラーなら器官劣等性である。行動療法はこのような病理理論を持たなかった。あえて言えば実験神経症があるが、似て非なるものである。Pavlov I.が犬に対してレスポンデント条件づけを行ったときに条件刺激の弁別を段階的に困難にさせていくと、ある時点で犬が吠えたり、噛みついたりするなどの異常行動を示すようになった。一度そうなると条件刺激を元に戻しても、前のようには弁別学習が進まなかった。この現象をPavlovは実験神経症と呼んだ。
言い換えると他の精神療法では“異常状態”が最初からあることを前提にして、その成り立ちを説明する理論がある。行動療法は犬でも人でもどんなに正常な状態であっても環境条件を操作すれば、異常に変えることができることを示した。この点で行動療法は二項対立を超えている。正常と異常は連続だと見做す。犬と人もそうだ。心と体もそうだ。行動主義の祖であるWatson J.は、健康な1ダースの乳児と、育てる事のできる適切な環境さえととのえば、才能、好み、適正、先祖、民族など遺伝的といわれるものとは関係なしに、医者、芸術家から、どろぼう、乞食まで様々な人間に育て上げることができると唱えた。行動療法は生まれ育ちや気質などの種別にもこだわらない。もちろん診断分類にもこだわらない。行動療法の初期の治療報告は単一事例が中心であり、それを誇りにもしていた。単一事例実験計画(D. Barlow & Hersen, 1997)のような証明方法を開発し、一人一人の患者さんにあわせてテーラーメードの治療を行うことでも科学的知見を得られた。
私は1986年に国立肥前療養所に就職した。ほとんどが開放病棟だった。山上敏子先生と行動療法があった。神戸大学から来た私にとって何よりも驚いたのは強迫症を治せるということだった。クロミプラミンの有効性もここでは衆知のことだった。ここでの行動療法では、患者一人一人で治療期間が違うのが常識だった。全員が同じ回数同じ期間治療を受ければそれで良い、と主張することは行動療法を知らないと言っていることと同じだった。診断毎・分類毎に治療の適応がある、たとえば知的水準が高い人には認知療法、中間の人には認知行動療法、低い人には行動療法というような治療適応があるという主張を目にすると山上先生は目をつり上げた。行動療法の適応がない診断・分類はない、たとえどんな状態であっても行動療法には何かできることがある、というのが山上先生の持論だった。当時の私はそこまで言うか?と思ったが、今の私なら賛成する。Gawande, Aの「死すべき定め」(Gawande, 2016)を翻訳したことも理由だ。5分前のことも忘れるような認知症の人でも、癌の末期で余命数日という人でも、その人がその人らしく生きる余地があり、支援できることがある。
V. EBMをし始めた頃:第二世代の行動療法~認知行動療法と認知モデル
1990年代に入ると行動療法“業界”に変化が起こる。“認知革命”と呼ぶ人もいる。Beck, ATやMeichenbaum D(Meichenbaum, 1977), Clark Dなどによる認知療法(Cognitive Therapy, CT)が入ってきた。Beckの功績はうつ病の成因に関する病理理論を提唱し、それを認知療法という独自の治療法パッケージに組み合わせたこと、そして群間比較のRCTを行ったことである。第一世代の行動療法家にとっては、いままで非科学的として遠ざけてきた素朴な常識心理学にも使いみちがあるという証拠をBeckが突きつけた形になった。行動療法は「心の病気は考え方次第でどうにでもなる」という常識を徹底的に否定することから始まっている。認知療法は考え方を変えることでできることもあることを示した。
Beckはもともと精神分析家である。しかし、彼の考えは精神分析学会では最初は受け入れられず、アメリカ行動療法学会(Association for Advancement of Behavior Therapy, AABT、現在のAssociation for Behavioral and Cognitive Therapies, ABCT)で発表することになった。認知療法のパッケージの中に行動療法の技法が入っていたので認知行動療法(Cognitive Behavior Therapy, CBT)と呼ばれるようになった。同時にこのころにDSM-III,III-R,IV,IV-TRとDSMが浸透した。DSMは精神分析による神経症概念も取り払い、それはそれまでの行動療法にとっての最大のライバルだった精神分析が米国精神医学の表舞台から退場させられたことを意味した。精神分析的精神病理理論はCBTの認知モデルに置き換えられた。パニック障害なら身体感覚に対する破局的解釈がある。社交不安障害なら安全確保行動と自己注目がある。強迫症なら責任の過大評価がある。
DSMがCBTに与えた恩恵のもう一つはパニック症や社交不安症、強迫症、全般性不安症、PTSDなどを独立させたことである。それまでの臨床試験ではこうした患者は十把一絡げに「神経症」にまとめられていた。それが細分化された診断について臨床試験を行えるようになった。精神療法各流派の中でエビデンス量、すなわちRCTとメタアナリシスの数を比較すればCBTの勝利は明白である。それは、診断を細分化してそれぞれにRCTを行えるようになったことも寄与しているのだろう。
1993年、感情障害長期経過追跡研究を通じて私は古川壽亮先生と出会った。これは私個人にとっては“EBM革命”だった。彼に手取り足取りされて論文も出している(原井, 1999)。EBMイコール治療のエビデンスだと思う人がいるかもしれない。もともとは臨床疫学と呼ばれ、検査や診断についても疫学的なデータに基づいて批判的吟味を行うものである。当時、私たちが熱中していたことは診断である。多施設共同による長期経過追跡研究のためには多様な個人を対象に均一な診断をつける必要がある。多様なのは患者だけでなく、診断者もそうである。こちら側を均質にするためには診断基準・治療マニュアルだけでなく、面接の仕方もマニュアル化する必要がある。その代表選手がSCIDである(First et al., 2003)。感情障害長期経過追跡研究でもCOALAを作った(Furukawa et al., 1995)。私自身でも物質使用障害患者を比較するために日本語と英語の面接を作った(原井宏明, 2001)。製薬企業からの受託研究では、M.I.N.I.(Sheehan et al., 1998)やSIGH-D(中根允文, 2003)、MADRS(上島国利, 2003)、PDSS(原井宏明, 山本育代, & 古川壽亮., 2004)、Y-BOCS(NAKAJIMA et al., 1995)などを使うのが当然になった。
この頃からの10年間の私を振り返ると半構造化面接漬けだった。通常の初診でもM.I.N.I.をしていた。うつであればSIGH-D,躁であればYMRS(稲田 et al., 2005)、パニック症であればPDSS、強迫症であればY-BOCS、社交不安ならLSAS(原井, 2003)、HARS-IG(大坪 et al., 2005)それぞれに合わせて重症度を評価していた。データは大量に集まる。そして、このまま集め続けてSPSSなどの統計パッケージを使えば新しい診断分類を提案できるだろうと思っていた。同時にこのころ、日本の精神医療がミステリーをやめるようになった。1987年,精神衛生法が精神保健法に変わった。1995年,“精神保健及び精神障害者福祉に関する法律”に変わり,精神障害者も障害者手帳を取れるようになった。患者に病名を告知して心理教育をすることが私を含めた精神科医の常識になった。私も白衣を着ることが普通になった。
VI. 動機づけ面接とACTをし始めた頃:第三世代~診断横断的アプローチ
2004年は私にとっての転換点である。動機づけ面接(Motivational Interviewing, MI)、アクセプタンス&コミットメントセラピー(Acceptance &Commitment Therapy, ACT)を使うようになった。知ったきっかけはEBMの習慣からである。系統的レビューを検索していたら、行動療法の仲間らしいのに私が全く知らないアプローチが出てきた。MIは従来のアルコール臨床の常識である“底つき体験”の必要性を否定している。ACTは行動療法からCBTに入ってきた私に取っては居心地の悪かった自動思考・認知再構成を乗り越えさせてくれそうだった。
どちらも診断横断的である。患者でも正常でも全ての人は基本的に同じ問題を抱えており,だから同じアプローチでよいと考える。第二世代の行動療法の進歩で大きな役割を果たしたBarlow, DHもUnified Protocol(不安とうつの統一プロトコル)(D. H. Barlow et al., 2012)を提唱した。これも診断横断的である。ライフスパン全体を考えれば、一人の人に不安とうつは共存することが多く、DSMに従えば併存診断(Comorbidity)が当然のように生じた。第二世代のCBTでは診断毎に別々の認知モデルをたてていた。併存診断を持つ患者に対してはこのやり方は意味不明である。
SCIDなどの半構造化面接は一回の面接で悉皆的に診断を探る。ハワイ州立精神病院で物質使用障害患者の診断面接を行っているときも依存症の患者はうつや精神病、不安症、パーソナリティーなど3つ以上の診断がつくことがごく当たり前だった。しかし、一人の人間に3つ以上の病名をつけて告知し、それぞれについて心理教育をすることは何の役にたつだろうか?たくさん病名をつけることは障害者手帳を取ることには都合が良いかもしれない。障害年金診断書を書くとき診断名が強迫症単独であれば却下されるが、うつ病も併存していることにすれば大丈夫である。でも治すことには?
心理教育も場合によっては有害である。アルコール依存症に対する酒害教育の逆効果はメタアナリシスをみれば歴然としている(Miller, Wilbourne, & Hettema, 2003)。救急場面では念入りな教育よりも短時間のMIの方がはっきりと効果的だ。うつやパニック症はもちろん、アルツハイマー病から高血圧まであらゆる診断に対して共通して効果を発揮する治療法の代表選手を一つ考えてみて欲しい。答えはプラセボだ。そしてプラセボは副作用がもっとも少ない。
実際にMIを使い出すと強迫症に対するエクスポージャーと儀式妨害(Exposure & Ritual Prevention, ERP)が楽に行えるようになった(原井, 2014)。それまでは無理矢理腕力でさせていたのである。父親にアルコール問題があり、自傷を繰り返していた社交不安症の若い女性にACT使ってみたら有効だった。境界性パーソナリティー障害らしさまで無くなってしまった(岡嶋美代 & 原井宏明, 2006)。
私は徐々に診断分類・半構造化面接への興味を失っていった。続けたのはM.I.N.I.ぐらいである。全般性不安症のようにうつ病の鑑別が難しく、私も慣れていない診断の場合には半構造化面接が必須だった。
2008年になごやメンタルクリニックに移るとM.I.N.I.も徐々にしなくなった。一日に最高で新患4人、再来が60人診るような場所では半構造化面接はやっていられない。強迫症のセルフヘルプ本(原井 & 岡嶋, 2012)を出したら、新患の7割が強迫症になった。強迫が初期値であり、患者も大半が行動療法を希望してくる。初診の30分で行うべきことは前医で出されている薬の整理と集団集中治療と個人カウンセリングの計画、簡単なホームワーク・セルフモニタリングの指示である。患者の約半数は前医の苦闘を物語るかのように長年、多剤併用になっていた。過去の病歴が分かっていれば他の疾患を除外することは難しくない。パーソナリティー障害や発達障害などを前医が見落としているかもしれないが、それらを診断するのはしばらくしてからでも遅くなかった。2,3週間ほどしてから、薬が1,2剤に整理され、セルフモニタリング記録もあるとなると初診時と比べると診断の精度が格段に高いのは当然だろう。よく考えてみれば初診時に全ての診断をつける必要はない。MIでは最初の課題は患者との関係性を作ることである。それさえできていれば、最初の日から解決策を提示する必要はない。
今日詳しく話を聞かせてもらいました。どうして自分がこんなに苦しいのか、理由か病名を知りたいのですね。原因がなければ苦しいのは自分のせいだという意味になりますから、そう思われるのはもっともだと思います。
私の考えとしては、そうですね、詳しい病名はしばらく経過を見てから決めた方が良いと思っています。どんな治療が一番良いかもそれからの方が間違いが少ないでしょう。この次に書いていただいたセルフモニタリングの内容もみてそうしたいと思いますが、いかがですか?
VII. 診断はどう役立つのか?
診断がよって立つ基盤は何なのだろう?診断基準・半構造化面接は何の役に立っているだろうか?そもそも何のために診断が必要なのだろうか?普通の精神科医なら、診断の根拠は精神病理学や臨床疫学のような医学であり、診断基準・半構造化面接は信頼性・妥当性を確保するためのツールであり、適正な保険診療のためには診断が当然必要だと答えるだろう。いずれももっともに聞こえる。でも本当にそうだろうか?世界精神医学学会とWHOがまとめたInternational Classification in Psychiatry(邦題 精神科国際診断の展望)の序文にはこう書かれている(Stefanis, 1989)。
精神医学における分類は、精神医学が学問として成立する以前から存在していた。事実、精神医学それ自体が、分類から生じたのであった。
考えてみればそうだ。精神医学が成立するはるか昔、ギリシャ時代からうつ病はある。強迫症も12世紀、中世ヨーロッパでScrupulosity(几帳面さ、入念さ)という名称で呼ばれていた。15世紀には神学者でありパリ大学の総長であったJean Gersonが宗教的な熱心さ・生真面目さが無用な苦悩を生むことを警告し、信心もほどほどにせよと戒めている。これは今でいう縁起恐怖・道徳強迫である。精神医学など全く知らない素人の素朴な観察と診断がもとになって精神医学が生まれているのである。その逆ではない。
診断基準・半構造化面接はどうだろう?どこまで行っても100%完ぺきな信頼性・妥当性はあり得ないことは誰にでもわかっている。では、どの程度なら良いのだろう?30年前、信頼性・妥当性自体を気にしていなかったころと比べれば精神医学は信頼できるものになった。DSMもIIIから5まで細部をみれば確かに進歩している。しかし、どこまでの信頼性・妥当性があれば私たちはOKと言えるのだろう?そのためにどこまで手間暇をかけられるだろうか?一流の医学雑誌に受理されるために必要なレベルと、多忙なクリニックで必要なレベル、そして患者自身のために書かれたセルフヘルプ本に必要なレベルではみんな違う。診断の見落としは確かに問題だ。不眠を訴える患者が来たとき、睡眠時無呼吸を見落としてベンゾジアゼピンを投与したら、かえって悪化させる。DSM-5のうつ病の分類では特定用語という小さな扱いになっている季節型、いわゆる冬期うつ病は高照度光療法という特異な治療に反応する。初期治療で上手く行かなかったとき、慢性化したときには素朴な観察・診断には頼れない。何かのチェックリストが必要だ。DSM-5やM.I.N.I.もそのために役立ってくれるだろう。しかし、どちらも初期治療が上手くいかず、診断を最初から見直さなければならないとき、医師がまってしまっている落とし穴を教えてくれるツールとして作られたものではない。
そして、実は問題はもっと別のところにある。診断は精神医学のため、信頼性・妥当性のため、適正な保険診療のため、であるとしたら、患者はどこにいったのだろうか?診断は患者のためにどう役立つのだろうか?肥前療養所に入った時、最初に目についたのは玄関ロビーに掲げられた“The Most Important Person In This Hospital is the Patient.”だった。患者中心の医療は謳い文句としては誰でも知っている。では具体的に診断はどうすれば患者のためになったと言えるのだろうか?
VIII. 患者と医師のための診断
今の私にとっては「患者のための診断とは何か?」の答えは30年前よりももっと分からなくなっている。どうなるのか良いことなのかは患者に聞くことが必要だとは分かっている。しかし、何が自分のためになるのか、それをよく分からないからこそ患者はクリニックにきて医者のアドバイスを求めているのだ。精神病の患者だけではない。強迫症の患者でもそうだ。病名ではちょっとしたトラブルがあった。
患者 私の病名は強迫症です。薬はセルトラリンが出ています。ネットで調べたら、セルトラリンは強迫症には適応がありませんでした。健康保険組合から違反だと怒られたりしませんか?
原井 セルトラリンもSSRIの一つで強迫に効果があるとわかっています。確かに保険での承認はありませんが、うつ病の病名をつけているから、問題はありません。
患者 私にはうつはまったくありませんが。
原井 確かに長生きしたいといつもおっしゃっているし、意欲的ですからね。これは保険病名と言って一応つけておく病名です。まあ大丈夫です。みんなやっていますから。
患者 でも違反なんですよね。
原井 まあ、でもそこまで調べられたりしませんよ。初診時は確認症状がひどいせいで落ち込んでおられたし、あながち嘘とは言えないし。
患者 私は嘘や間違ったことには耐えられません。もし保険組合から問い合わせがあったらどう答えたらいいんですか?
原井 いや患者さんに問い合わせがあることはまずありません。
患者 絶対ないとどうして言えるんですか?(続く)
私は諦めてフルボキサミンに変更した。強迫行為に巻き込まれたわけである。初診時は警察官を見るだけで怯えるような患者だった。その頃よりはずいぶん改善し、日常生活は普通にできるようになった。しかし、このような拘りのために人間関係にトラブルが生じることがまだあった。風邪で受診した内科医院でも同じようなことをしたらしい。
しばしば患者は普通になりたいという。病気になる以前に戻りたいとも言う。記憶を消したいという人もいる。“普通”を定めた診断基準はどこにも存在しない。病気になり、受診し、治療を受けているという事実と記憶はどれだけ良くなったとしても消えることはない。診断は一つのツールであり、スタート地点である。その先は精神医学や診断基準もないところを患者と一緒に探していかなければいけない。
IX. 最後に
精神療法を観念主義と実際主義に二分するとしたら,実際主義の極にあるのが行動療法である。実際主義とはプラグマティズムのことであり,「経験不可能な事柄の真理を考えることはできない」と主張するイギリス経験論を引き継いで、20世紀初頭のアメリカで花開いた。行動療法は実際主義の伝統の上に立ち、私たちの常識的な観念を疑ってかかる。私たちはいろんな二分法の中で育ち、それを常識とし、疑いもしない。もっとも根強いものは心と体であり、思考と行動、正常と異常だろう。行動療法はそんな常識を覆すところから始まった。自分自身のあり方も覆している。行動一本槍になったり、認知に走ったり、また再び行動に戻ったりする。このような変わる能力をもっていることが行動療法の最大の強みである。私自身も変わった。それは行動療法のおかげであり、EBMのおかげでもある。Sacketが最初に行ったEBMの定義には”External Evidence”外部のエビデンスという言葉が繰り返しでてくる(Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996)。自分自身を育ててくれた文化・流派から外れた所からエビデンスを拾ってこいとSackettは繰り返し主張しているのだ。自分が馴染んだ世界からだけものを見るようにしていれば,ものは必ず必ず歪んで見えており、何か大事なものを見落としていても気づかない。
医学は著しく進歩した。日本人の平均寿命は1985年から2015年の30年間に6年伸びた。女児だけに生じる特殊な自閉症とされていたレット症候群はX染色体上のMECP2遺伝子の突然変異が原因と判明し、DSM-5の病名リストから消えた。8項目の診断基準を一回の遺伝子検査が置き換えたわけである。ずっと長い間、肝硬変経由肝癌行きの片道切符だったC型肝炎は2014年からは治癒する病気になった。直接作用型抗ウイルス剤が使えるようになったからだ。医学は一部の疾患についてはパズルをクリアに解き明し、文句のつけようのない解決も提示できることがある。一方で大半の疾患についてはミステリーのままだ。そして大半の医師にとっては医学の謎のどれがパズルでどれがミステリーか、この二分法自体がミステリーであり、しかも毎日新しい謎が付け加わる。
30年やっても医学は相変わらず面白い。
謝辞
- この原稿を書くに当たり、都立松沢病院精神科の今井淳司先生に貴重なコメントを頂いた。伝統的な精神病理学に立つ方にも興味を持って頂ける文章だとしたら、それは全て彼のおかげである。
- 診断をパズルとミステリーに分けたのは、Malcolm Gladwellによる“Open Secrets”からのアイデアである。http://gladwell.com/open-secrets/
文献
Barlow, D. H., 伊藤正哉(臨床心理士), 堀越勝(心理学), Farchione, T. J., Fairholme, C. P., Ellard, K. K., … Ehrenreich-May, J. T. (2012). 不安とうつの統一プロトコル : 診断を越えた認知行動療法. 診断と治療社. Retrieved from http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB09159438
Barlow, D., & Hersen, M. (1997). 一事例の実験デザイン―ケーススタディの基本と応用 (p. 297). 大阪: 二瓶社.
First, M. B., Gibbon, M., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W., 北村俊則, 富田拓郎, … 高橋三郎. (2003). 精神科診断面接マニュアルSCID. Book, 東京: 日本評論社.
Furukawa, T., Takahashi, K., Kitamura, T., Okawa, M., Miyaoka, H., Hirai, T., … Fujita, K. (1995). The Comprehensive Assessment List for Affective Disorders (COALA): a polydiagnostic, comprehensive, and serial semistructured interview system for affective and related disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica. Supplementum, 387, 1–36. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7793293
Gawande, A. (2016). 死すべき定め―死にゆく人に何ができるか. 東京: みすず書房.
Meichenbaum, D. (1977). Cognitive-Behavior Modification, An Integrative Approach. New York: Plenum Press. http://doi.org/10.1007/978-1-4757-9739-8
Miller, W. R., Wilbourne, P. L., & Hettema, J. E. (2003). What works? A summary of alocohl treatment outcome research. In R. K. Hester & W. R. Miller (Eds.), Handbook of alcoholism treatment approaches: Effective alternatives (3rd ed.). (pp. 13–63). Book Section, Needham Heights, MA, US: Allyn & Bacon.
NAKAJIMA, T., NAKAMURA, M., TAGA, C., YAMAGAMI, S., KIRIIKE, N., NAGATA, T., … YAMAGUCHI, K. (1995). Reliability and validity of the Japanese version of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 49(2), 121–126. http://doi.org/10.1111/j.1440-1819.1995.tb01875.x
Reichow, B., Barton, E. E., Boyd, B. A., & Hume, K. (2012). Early intensive behavioral intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD). The Cochrane Database of Systematic Reviews, 10, CD009260. http://doi.org/10.1002/14651858.CD009260.pub2
Sackett, D. L., Rosenberg, W. M., Gray, J. A., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. Bmj, 312(7023), 71–72. Journal Article. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=8555924
Sheehan, D. V, Lecrubier, Y., Sheehan, K. H., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, E., … Dunbar, G. C. (1998). The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry, 59 Suppl 2, 22–57. Journal Article. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=9881538
Stefanis, N. C. (1989). 序文. In J. E. Mezzich & M. Cranach (Eds.), International Classification in Psychiatry, Unity and Diversity (精神科国際診断の展望). Cambridge: University Press.
稲田俊也, 稲垣中, 岩本邦弘, 中谷真樹, 堀宏治, & 樋口輝彦. (2005). ヤング躁病評価尺度日本語版(YMRS-J)による躁病の臨床評価 = Clinical evaluation of manic disorders by the Japanese version of Young Mania Rating Scale (YMRS-J). じほう. Retrieved from http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA72084746
岡嶋美代, & 原井宏明. (2006). 境界性人格障害と呼ばれそうな20代女性に対するSADグループ治療. In 日本行動療法学会第32回大会発表論文集 (pp. 82–83). Conference Proceedings, 東京都.
原井宏明. (1999). エビデンス精神医療手取り足取り 3 エビデンスの検索. 臨床精神医学, 28(10), 1285–1291. Journal Article.
原井宏明. (1999). 感情障害長期経過多施設共同研究厚生省精神・神経疾患研究10年度研究報告書感情障害の成因解明,治療法の標準化 及び治療反応性の予測因子に関する研究 (pp. 63–66). Book Section.
原井宏明. (2001). 諸外国との比較 3年間のまとめ 治療に関するレビュー・北部九州とハワイの物質使用障害患者の比較. 厚生科学研究補助金 医薬安全総合研究事業10~12年度研究報告書 薬物依存・中毒者のアフターケアに関する研究. Generic.
原井宏明. (2003). 【社会不安障害(SAD)の薬物療法】 社会不安障害の薬物療法のエビデンス. 臨床精神薬理(1343-3474), 6(10), 1303–1308. Journal Article.
原井宏明. (2014). 強迫性障害の認知行動療法-個人療法,集団集中治療,サポートグループ. In 原田誠一 (Ed.), メンタルクリニックが切り拓く新しい臨床 (pp. 99–108). 東京: 中山書店.
原井宏明, & 岡嶋美代. (2012). 図解やさしくわかる強迫性障害 : 上手に理解し治療する. 東京: ナツメ社. Retrieved from http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB09312342
原井宏明, 山本育代, & 古川壽亮. (2004). パニック関連障害 PDSS,自記式尺度. In 樋口輝彦, 久保木富房, 中村純, & 山脇成人. (Eds.), ストレス疾患ナビゲーター (Vol. 108–109). Book Section, 東京: メディカルレビュー社.
古川壽亮, & 神庭重信. (2003). 精神科診察診断学 エビデンスからナラティブヘ. 東京: 医学書院.
上島国利. (2003). Montgomery asberg Depression rating Scale (MADRS)の日本語訳の作成経緯. 臨精薬理, 6, 341–363. Retrieved from http://ci.nii.ac.jp/naid/50000765235/en/
青木典太, 遠藤四郎, & 中井久夫. (1984). 精神科治療の手引き. 神戸: 神戸大医学部精神科.
大坪天平, 幸田るみ子, 高塩理, 田中克俊, 衛藤理砂, 尾鷲登志美, … 上島国利. (2005). 日本語版Hamilton Anxiety Rating Scale-Interview Guide(HARS-IG)の信頼性・妥当性検討. 臨床精神薬理, 8(10), 1579–1593. 原著論文. Retrieved from http://search.jamas.or.jp/link/ui/2005285849
中根允文. (2003). HAM-Dの構造化面接SIGH-D日本語版について. 臨床精神薬理, 6(10), 92–97. Retrieved from http://ci.nii.ac.jp/naid/50000296694/en/
浜副薫. (1985). 14 曝露-反応妨害法が有効であった強迫神経症の4症例(一般演題C). 日本行動療法学会大会発表論文集, (11), 46–47. Retrieved from http://ci.nii.ac.jp/naid/110009671036/en/
満田久敏. (1968). 精神医学における臨床と遺伝 非定型精神病の問題を中心にして. 精神医学, 10(3), 185–190. Retrieved from http://ci.nii.ac.jp/naid/40017963734/en/